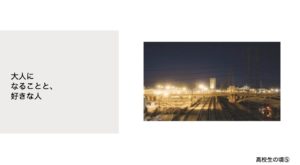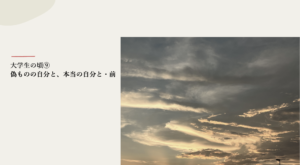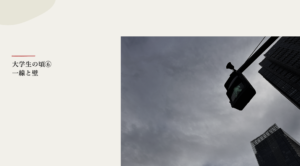前回の記事はこちらから。

高校生の頃の話4回目です。どうぞ。
古本の匂いと斜陽
一、二年生のころ、学内で委員会というものがあった。
何かしらの委員会に入る必要があり悩んだのだが、彼に「一緒にやろ」と言われ、同じ図書委員会にはいることができた。
図書委員は、お昼休みや放課後図書室の管理をする。
仕事内容はイメージ通り。本の貸し借りを受け付けたり、本の整頓をしたり。
加えて、CDやDVDの貸し出しもした。
そういった管理をしつつも、図書室に置いてほしい「リクエスト」の処理もする。
図書室での仕事は、彼と一緒にいられるいい口実にもなった。
校舎は七階建てで、都会の真ん中にある。異様に縦に長い校舎だ。
最上階に図書室は位置しており、そこそこの景色が臨めた。
放課後、いつもの仕事をしに図書室に入る。
古い紙のにおいがうっすらとするこの部屋は、窓から入り込む西日の色で、淡く色づいていた。
窓から校門付近に目を下ろすと、下校する者、部活に向かう者がいる。
一人一人に別々の生活があると思うと、なんだか不思議な気持ちになった。
同じ学校、同じクラスであっても、みんな別々の暮らしがある。僕はどれくらいの人と関わるのだろう。
窓から見える人々は、きっと僕とは関わらない。関わらずして、各々の人生を過ごしていく。
そしてきっと、今仲良くしている人たちも、卒業後ずっと関わり続けることは稀であろう。
好きな人とは…この先も、今のように仲良くいれるのだろうか。
ちょっとした不安が胸をかすめた。
今と、この先の将来と。
「おまたせ。」
おくれて彼がやってきた。
ああ、そうだ。
彼は今ここにいて、僕の手の届くところにいてくれる。
そう思うだけで、先の不安はすぐに消えてしまった。
あの頃の僕は、一日一日を刹那的に生きていた。
そうでもしない限り、先の見えない不安で溺れてしまいそうだったから。
同じ性別の男の子を好きになってしまった。そんな人の未来なんて、聞いたことが無かった。
将来について考える度、胸のあたりが重くなって、呼吸が浅くなる。
息をしなくちゃ。溺れそうな日が続いているとしても。
立ち止まって 君がいないかなんて 探しちゃうんだよ。
あの頃聞く歌は不思議なほどに、あの頃の自分とよく重なる。
そしてそんな歌との出会いも、あの図書室で手にしたアルバムがきっかけだった。
静かな喧騒と、高揚
図書室での仕事は、生徒が来ない限り暇だった。
カウンター内でおしゃべりしたり、図書室の中にあるソファーでくつろぐこともできた。
本を棚に戻しながら、たわいもない話をして過ごす。
彼は図書室の中をぐるぐると歩き回り、小声で歌いながら仕事をしている。
気づけば、図書室には誰もいなくなっていた。
突然、歌が止んだ。
本棚の隙間越しに、彼と目があう。
「誰もいないね。」
そう言う彼の目元は笑っていた。
図書室の静けさに今二人きりなんだと、急に意識させられる。
どこかで、楽器の音色が響いている。
その後ろから、運動部の音や声が聞こえる。
外の喧騒が、ぼんやりと校舎内を流れ、入り込む。
目の前が静かで、遠くの方の音が聞こえてくる、そんな感覚。
西日、遠くの楽器の音、運動部の声、そして古本の匂い。
一つ一つがどうしてか淡い。胸をうつ自分の音が、聞こえるくらいに。
放課後の図書室に、思いを寄せる人とふたりきり。
何かいけないことでもしているような、不思議な高揚感にどきどきした。
〇
仕事をすませた後、修学旅行について話した。
行先はマレーシア。なんとも特徴的な旅先だ。
「部屋、どうなるんだろうね。」
「二人か三人部屋らしいよ?」
「え、やっぱそうなの?」
修学旅行の部屋割りは気になるものだった。それも大部屋ではなく個室ともなれば、彼と一緒が良い。
「一緒の部屋でもいいよ。」
彼はそう口にした。
あまりにあっさりとそんなことを口にするので、拍子抜けするほどだった。
まさかそんな風に言ってもらえるとは思わなかった。
「別にいいけど…」
「じゃあ俺はベットの下に隠れるね?笑」
「え、なんで」
「おもしろいじゃん。」
何がおもしろいのだろう。
それが分からなくて、でもそんなことを言う彼がおもしろくて、笑ってしまった。
相も変わらず、彼は少し変だ。でもそういうところが子供らしくて、かわいくて、好きだった。
修学旅行はまだ先のことだ。でも、少しだけわくわくした。
やっぱり彼と一緒にいると楽しい。
彼はきっと、僕が喜んでいることにも気づかなかっただろう。
静かに喜びを噛みしめながら、図書室を後にした。
そのうちの、一人に。
彼と別れ、校舎を出る。先の喧騒がうるさいほどに聞こえてきた。
そうして図書室から見降ろしていた「みんな」のうちの一人に、自分も混ざった。
友達も、周りにいる人たちも、やがては卒業し自分の人生を歩んでいく。
それは彼も例外ではない。
僕は、そんな未来に見て見ぬふりをしていた。
制服のポケットからイヤフォンを取り出し、喧騒に耳をふさぐ。
夕暮れ時の濃ゆい紫色の空が、ビルの隙間から覗いていた。
続きはこちらから