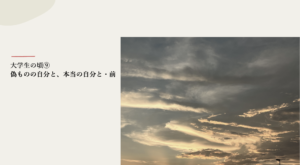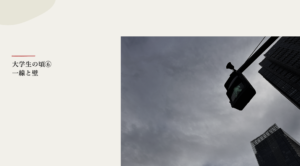前回の『高校生の頃①』はこちらから。

では、続きます。
帰り道と、デート
今思い返しても、思い出すのは、初めて彼の地元に行って、そこで始めて彼と会った瞬間。
彼が帰る道
いつも、彼が帰る道をなぞる。
下校する際、普段バイバイと言ってわかれる、改札に入る。
どれも新鮮だった。
彼の地元は、学校の最寄り駅から30分ほどかかる。少しばかり遠い距離とも言えなくはないが、それも苦にはならなかった。
「こんな道で、こんな風に歩いているんだ」と、彼の見る世界に少しだけ、近づけた気がした。
途中、車窓の景色が緑一色になった。
たった30分電車にのるだけで、ここまで景色が変わることに驚いた。
子供のように、ずっと外を眺めていた。
○
電車は終着駅につく。
彼の地元は、路線の端にあった。
大きな駅で、ショッピングモールと繋がっていた。
待ち合わせ場所に早くついてしまった。
その後少しして、彼がやってきた。
にやにやしながら柱に隠れるようにして、おどけるしぐさを見せる。
子供みたいで、それがすごく、彼らしい。
思わず僕も頬が緩んでしまった。
「遠かったっしょ」
「遠いね。毎日大変じゃない?」
「もう慣れた。笑」
たわいもない話をしながら、ショッピングモールを散策した。
おしゃれな洋服屋さんが軒を連ね、見ているだけで楽しかった。
「この服がいいね!」と彼が思う、僕らしい服を合わせたりもした。
帽子を試着し合ったりもして、心なしかデートをしている気分になれた。
でもきっと、そう思っていたのは僕だけだ。
独りよがりな気持ちではあったけれど、嬉しかった。
自分たちと同じくらいの年で、制服で歩いている男女とすれ違った。
きっと普通のカップルは、好きな人とこういうことをするんだろうな…
「本物の」デートをしているカップルを横目に、そんなことを思った。
でも、その時ばかりは気にならなった。
それくらい彼と二人で遊べることが、楽しかったのかもしれない。
お店をまわるうちに、一軒のアパレルショップでメンズ向けのアクセサリーを扱うお店があった。
「これかっこいいな…」
「いいね。つけてみたい」
そんなことを言いながら、お店をあとにした。高校生にとっては、少し値が張りすぎていた。
社会人になった僕からすれば、デート先でショッピングすることも容易いのだろう。
でも、この時の僕は将来のことなんて思いもしなかった。
あの時は、今を生きることで精一杯だった。
僕が帰る道
「そろそろ帰ろうか。遠いもんね。」
日がかげり、帰る時間になってしまった。
ばいばいとハイタッチをして、改札を通る。
彼とわかれる時は、決まって手を合わせた。
その時の彼の顔も、笑顔だった。
もうほとんど沈みきっている日が、最後の薄い光を残して夜を連れてくる。
その境、もう夜になるという瞬間、空は濃ゆい紫になる。
そんな空を背に、田園風景が流れていった。
イヤフォンから流れる音の後ろから、電車のアナウンスが聞こえる。
帰り道は、いつも感傷的になってしまうから嫌いだ。
あれほど楽しかったにも関わらず、帰り道はいつも寂しさを覚える。
そして、現実を見せるんだ。
イヤフォンの音を上げ、そこから流れる音楽に集中しようとしても、だめだった。
○
家につき、自分の部屋にこもる。
でも寝る時は家族共有の部屋で寝なければならず、
それが苦痛だった。
泣いてしまうのを抑えながら寝ないといけない。
夜中、隣で寝ている家族が寝静まったのを見て、僕はベランダにでた。
熱帯夜と言えど、夜の風は心地よかった。
「楽しかったのにな…」
小さくかすれた声が、風に流れる。
あんなに楽しかったのに、いつもだめなんだ。
それがつらくてたまらない。楽しければ楽しい程、つらい気持ちで上塗りされていく。
きっとこれはもう、「友達」としての「好き」じゃないんだろうな。
そう思わざるを得なかった。
泣かないように、顔を上げる。
半分の月だけが、孤独に光っていた。
続きはこちら